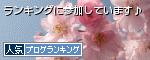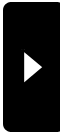食 ~【茶丈 藤村】のおぜんざい~
以前もご紹介しましたが、石山寺近くの【茶丈 藤村】にて、今年もおぜんざいを食べてきました!

年明けのおめでたい雰囲気のときには無性に食べたくなるおぜんざい。
こんがり焼き目のついた近江米のお餅が本当に美味しい!
あずきももちろん美味しくて、この甘みとお餅の伸び具合がたまりません!
幸せをかみしめる瞬間です。
友人と共にお座敷で長時間に渡ってお喋りをしていたのですが、あたたかいお茶のおかわりまでいただいて大変くつろぐことができました。
ほっこり心も温まったひととき。
美味しそうな柚子のおまんじゅうをお土産に買って、ほくほく気分で帰宅です。

石山寺近辺にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
▼押してもらえると励みになります♪
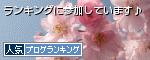


年明けのおめでたい雰囲気のときには無性に食べたくなるおぜんざい。
こんがり焼き目のついた近江米のお餅が本当に美味しい!
あずきももちろん美味しくて、この甘みとお餅の伸び具合がたまりません!
幸せをかみしめる瞬間です。
友人と共にお座敷で長時間に渡ってお喋りをしていたのですが、あたたかいお茶のおかわりまでいただいて大変くつろぐことができました。
ほっこり心も温まったひととき。
美味しそうな柚子のおまんじゅうをお土産に買って、ほくほく気分で帰宅です。

石山寺近辺にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
▼押してもらえると励みになります♪
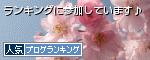
◎ ~長等山 園城寺(三井寺)~
お寺の話題が続きますが、西国三十三所第十四番札所である長等山 園城寺(ながらさん おんじょうじ)=通称:三井寺(みいでら)もこの秋に行ってきました!
※撮影日2019/11/21
紅葉はまだ青い部分も多く、でも私が一番好きなグラデーションで個人的には見頃!
全部が真っ赤よりも、黄緑や橙色がある方がその配色の妙が堪りません!


三大名鐘の「三井の晩鐘」の周辺も綺麗でしたよ。


札所の御朱印が貰える観音堂は一番の高台にあって、その更に上の「大津そろばんの碑」まで登ると絶景が見られます!


その御朱印がこちら

西国三十三所草創1300年記念事業の特別印は、「三井の晩鐘」で有名な鐘と桜。

紅葉もオススメですが、桜の時期も綺麗なんですよねぇ。
ちょうど秘仏の公開中で、日本三大不動の一つ、「黄不動尊」(存在自体を初めて知りました。勉強不足です・・・)を間近で見ることができました。
(ちなみに他の2つの不動尊、青は京都の青蓮院、赤は高野山の明王院にあるそうです。)
記念に黄不動尊と金堂の弥勒仏の御朱印もいただきました。

紅葉に秘仏に他の仏像や御守り、孔雀、びわ湖の景色と、見どころ満載でなかなかに充実した1日に。
境内の茶屋で一服できなかったのが心残りなのでまたリベンジに来たいと思います!
そして意図的にではないですが、今年1年で大津市内にある3か所の札所すべてで特別印をいただくことができました!
この勢いで来年もいろんな社寺にお参りに行けたら良いなと思います。
2020年もおつきあいのほど、よろしくお願いいたします。
少し早いですが、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
▼押してもらえると励みになります♪
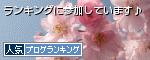

※撮影日2019/11/21
紅葉はまだ青い部分も多く、でも私が一番好きなグラデーションで個人的には見頃!
全部が真っ赤よりも、黄緑や橙色がある方がその配色の妙が堪りません!


三大名鐘の「三井の晩鐘」の周辺も綺麗でしたよ。


札所の御朱印が貰える観音堂は一番の高台にあって、その更に上の「大津そろばんの碑」まで登ると絶景が見られます!


その御朱印がこちら

西国三十三所草創1300年記念事業の特別印は、「三井の晩鐘」で有名な鐘と桜。

紅葉もオススメですが、桜の時期も綺麗なんですよねぇ。
ちょうど秘仏の公開中で、日本三大不動の一つ、「黄不動尊」(存在自体を初めて知りました。勉強不足です・・・)を間近で見ることができました。
(ちなみに他の2つの不動尊、青は京都の青蓮院、赤は高野山の明王院にあるそうです。)
記念に黄不動尊と金堂の弥勒仏の御朱印もいただきました。

紅葉に秘仏に他の仏像や御守り、孔雀、びわ湖の景色と、見どころ満載でなかなかに充実した1日に。
境内の茶屋で一服できなかったのが心残りなのでまたリベンジに来たいと思います!
そして意図的にではないですが、今年1年で大津市内にある3か所の札所すべてで特別印をいただくことができました!
この勢いで来年もいろんな社寺にお参りに行けたら良いなと思います。
2020年もおつきあいのほど、よろしくお願いいたします。
少し早いですが、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
▼押してもらえると励みになります♪
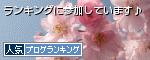
◎ ~石光山 石山寺~
岩間寺に続き、西国三十三所第十三番札所である石光山 石山寺(せっこうざん いしやまでら)に行ってきました!
※撮影日2019/11/16(1枚目の門のみ別日程)

この日は本堂などにはお参りせず参道だけちらっと覗いて来たのですが、ここだけでも紅葉が十分楽しめます。
(※レンズが曇っていたらしく、最初の数枚はボカシがかかっています)



池に映った紅葉のグラデーションもまた綺麗です。

御朱印は今年の元日にいただいたもの。

まだ平成表記です。
西国三十三所草創1300年記念事業の特別印は、言わずもがな紫式部ですね。

平安時代、京都の貴族の間で石山詣が流行っていたそうで、紫式部はここ石山寺で『源氏物語』の構想を練ったと言われています。境内には紫式部の像もありますので、ご興味のある方はそちらもぜひご覧ください。
また、石山寺のご本尊は日本で唯一の勅封(天皇の命令によって封印されている)秘仏で、33年に一度しか御開帳されません。が、天皇のご即位にあたり来年2020年に特別公開があるそうです!
通常公開は約30年後ですので、この機会にぜひ。
桜や躑躅、青もみじの季節もオススメです。
▼押してもらえると励みになります♪
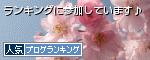

※撮影日2019/11/16(1枚目の門のみ別日程)

この日は本堂などにはお参りせず参道だけちらっと覗いて来たのですが、ここだけでも紅葉が十分楽しめます。
(※レンズが曇っていたらしく、最初の数枚はボカシがかかっています)



池に映った紅葉のグラデーションもまた綺麗です。

御朱印は今年の元日にいただいたもの。

まだ平成表記です。
西国三十三所草創1300年記念事業の特別印は、言わずもがな紫式部ですね。

平安時代、京都の貴族の間で石山詣が流行っていたそうで、紫式部はここ石山寺で『源氏物語』の構想を練ったと言われています。境内には紫式部の像もありますので、ご興味のある方はそちらもぜひご覧ください。
また、石山寺のご本尊は日本で唯一の勅封(天皇の命令によって封印されている)秘仏で、33年に一度しか御開帳されません。が、天皇のご即位にあたり来年2020年に特別公開があるそうです!
通常公開は約30年後ですので、この機会にぜひ。
桜や躑躅、青もみじの季節もオススメです。
▼押してもらえると励みになります♪
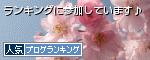
◎ ~岩間山 正法寺(岩間寺)~
西国三十三所第十二番札所である岩間山 正法寺(いわまさんしょうほうじ)=通称:岩間寺(いわまでら)に行ってきました!
※撮影日2019/11/9
御朱印帳を持つ前に仕事で行ったことがあったのですが、プライベートでちゃんとお参りするのは初めてでした。

結構な山道でしたが、それだけ高い所に来たということは景色が抜群!

京都は宇治との境にある山ということで見晴らしが良かったです。
紅葉には少し早いくらいの時期でしたが、山の上ということもあってキレイに色づいていました。

参道を抜けて本堂へ向かいます。

ど真ん中には立派な大イチョウの巨木が!

本堂でお参りして御朱印をいただきました。

本堂の横にある池にもご注目ください!

松尾芭蕉が「古池や 蛙飛び込む 水の音」という俳句を詠んだ場所と言われています。
運が良ければ本物の蛙が見られるかも?
こちらは分かりにくいですが、日本一の桂の大樹群。左の方に幹が見えます。

散策してみると、幻想的な池もありました。

そしてこちらが御朱印。


西国三十三所草創1300年の特別印と、菊の紋は天皇ご即位記念の印(追加料金要)も押してもらいました。
特別感があって嬉しいです!
▼公式HPより
泰澄大師が当地に伽藍建立の際、たびたび落ちる雷に困り果て、ご自分の法力で雷を封じ込め、落ちる訳を尋ねられたところ、雷は大師の弟子になりたいのだと申し出た。大師は快く雷を弟子にし、その代わりに岩間寺に参詣の善男善女には、雷の災いを及ぼさないことを約束させた。これが「雷除け観音」とよばれる由縁で、毎年四月十七日には、雷除け法要(雷神祭)が奉修され、多くの参詣者で賑わう。
▼押してもらえると励みになります♪
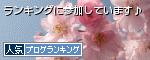

※撮影日2019/11/9
御朱印帳を持つ前に仕事で行ったことがあったのですが、プライベートでちゃんとお参りするのは初めてでした。
結構な山道でしたが、それだけ高い所に来たということは景色が抜群!
京都は宇治との境にある山ということで見晴らしが良かったです。
紅葉には少し早いくらいの時期でしたが、山の上ということもあってキレイに色づいていました。
参道を抜けて本堂へ向かいます。
ど真ん中には立派な大イチョウの巨木が!
本堂でお参りして御朱印をいただきました。
本堂の横にある池にもご注目ください!
松尾芭蕉が「古池や 蛙飛び込む 水の音」という俳句を詠んだ場所と言われています。
運が良ければ本物の蛙が見られるかも?
こちらは分かりにくいですが、日本一の桂の大樹群。左の方に幹が見えます。
散策してみると、幻想的な池もありました。
そしてこちらが御朱印。
西国三十三所草創1300年の特別印と、菊の紋は天皇ご即位記念の印(追加料金要)も押してもらいました。
特別感があって嬉しいです!
▼公式HPより
泰澄大師が当地に伽藍建立の際、たびたび落ちる雷に困り果て、ご自分の法力で雷を封じ込め、落ちる訳を尋ねられたところ、雷は大師の弟子になりたいのだと申し出た。大師は快く雷を弟子にし、その代わりに岩間寺に参詣の善男善女には、雷の災いを及ぼさないことを約束させた。これが「雷除け観音」とよばれる由縁で、毎年四月十七日には、雷除け法要(雷神祭)が奉修され、多くの参詣者で賑わう。
▼押してもらえると励みになります♪
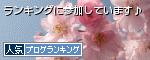
◎ ~【大津祭2019】本祭~
日本に甚大な被害をもたらした台風19号が去った10月13日。
爽やかな秋晴れのもと、大津祭は無事に開催されました。

宵宮は中止になり、人出も少ないじゃないかと心配でしたが、
本祭当日はとても賑わっていて良かったです。



お茶のお店、中川誠盛堂さんの店頭にはミニチュアの曳山と提灯がディスプレイされていました。

今年も元気に大津の秋の風物詩を観ることができたことに感謝です。
さて、今週末はおおつ花フェスタや大津ジャズフェスティバルなど、まだまだ秋のイベントは盛りだくさん!
大津の秋を楽しみましょう♪
▼押してもらえると励みになります♪
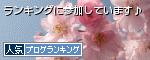

爽やかな秋晴れのもと、大津祭は無事に開催されました。

宵宮は中止になり、人出も少ないじゃないかと心配でしたが、
本祭当日はとても賑わっていて良かったです。



お茶のお店、中川誠盛堂さんの店頭にはミニチュアの曳山と提灯がディスプレイされていました。

今年も元気に大津の秋の風物詩を観ることができたことに感謝です。
さて、今週末はおおつ花フェスタや大津ジャズフェスティバルなど、まだまだ秋のイベントは盛りだくさん!
大津の秋を楽しみましょう♪
▼押してもらえると励みになります♪